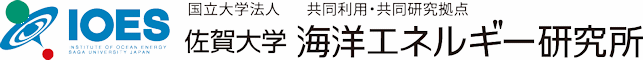海洋温度差発電の分類
海洋温度差発電(OTEC)の分類OTECは、海水の利用法と発電法によって次のように分類できます。
|
| 電子技術総合研究所 (ETL)[現:産業技術総合研究所 AIST] のETL-OTEC(1975年9月~) | |
| 米国ロッキード社他のMini-OTEC[バージ形](1979年8月) | |
| 米国エネルギー省(DOE)のOTEC-1実験プラント[バージ形] (1980年4月~1981年11月) |
|
| ナウル共和国の陸上設置型OTECプラント[陸上設置型](1981年10月) | |
| 佐賀大学OTEC実験用プラント[陸上設置型] | |
| インド国立海洋技術研究所のSAGAR-SHAKTI(OTECプラント)[バージ形](実験中止) |
等、最近のOTECでは主流である。
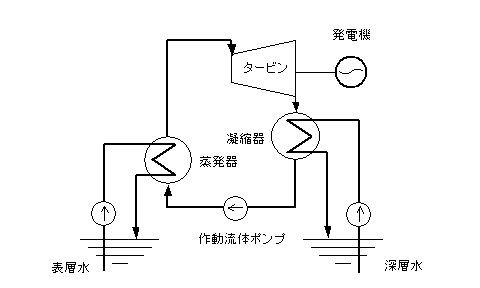
オープンサイクル (Open Cycle)
G.クロード(Georges Claude)が考案したサイクル。クローズサイクルと同様、蒸発器・凝縮器・タービン・発電機から成るが、構造上作動流体を循環させる必要がないため、作動流体ポンプは存在しない。このシステムでは、蒸発器、タービン、凝縮器内をあらかじめ真空ポンプで真空にしておく。次に、温海水を蒸発器内に導入して蒸発させて水蒸気を得る。この水蒸気を作動流体として、タービンに送り、タービンを回して発電を行う。タービンから出た膨張した水蒸気は凝縮器に入り、冷海水によって冷却され、海に排出される。この様に作動流体である水蒸気はサイクル内を循環しないのでオープンサイクルと呼ばれる。 (OC-OTECと呼ばれる。) なお、排出した水は飲料水としても使用できる。このサイクルについては、日本ではほとんど研究されていないが、フランス政府は現在でも積極的に研究を行っている。- 佐賀大学OTEC実験装置-不知火1号(1974年4月) [参考]
- Natural Energy Laboratory of Hawaii (NELHA)がハワイ島コナ海岸に建設したOTEC実験装置(1992-1998)
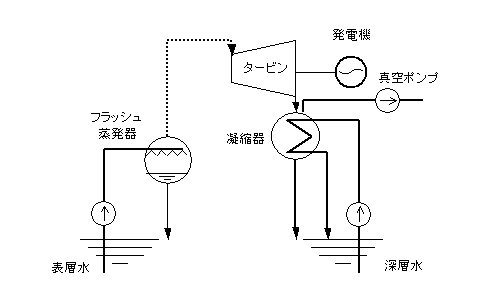
ハイブリッドサイクル (Hybrid Cycle)
クローズドサイクルとオープンサイクルを組み合わせたもの。基本構造はクローズサイクルであるが、蒸発器に導入する高温熱源が異なる。クローズサイクルでは、蒸発器に温海水を直接導入するのに対し、ハイブリッドサイクルでは、一旦オープンサイクルの蒸発器に温海水を導入し、そこで得られた水蒸気を高温熱源として使う。このことから、クローズサイクルに比べ、蒸発器の海水による汚染がなく、性能の低下が防げる。また、オープンサイクル同様、蒸発器から排出された水は、飲料水として使えるため、淡水化技術の応用として考えられている。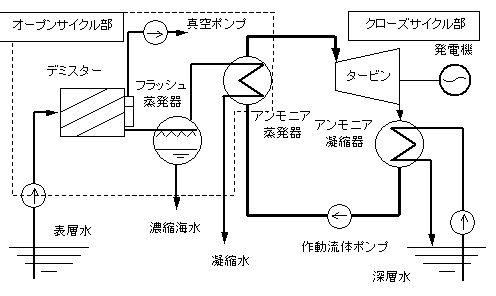
ミストサイクル (Mist Cycle)
Charwatらによって考案されたサイクル。構造体は半潜水形をとる。温海水を落下させ、位置エネルギーのみで水車タービンを回して発電する。タービンを出た海水は、ミスト(霧)発生器に導入され、霧となり上昇する。その後凝縮器に入り、冷却水である冷海水によって冷やされ、水となり排出される。フォームサイクル (Foam Cycle)
Zenerによって考案されたサイクル。構造体は半潜水形をとる。サイクル内に導入された温海水は、気泡発生器を通過する。発生した気泡と海水は、サイ クル上部に設けられた気泡ブレーカーによって海水と気泡に分離される。分離された海水は、そのまま落下して水車タービンを回して発電する。一方、気泡=水 蒸気は、冷海水よって冷却され水となり、海中に排出される。
■熱電方式
熱電方式 (Thermoelectric generation)
異種の金属を接触させる。その両端に温度差を与えた場合、起電力が発生する。これをゼーベック効果という。一般に、温度を測定する際に使われる熱電対の原理がこれであるが、これを海洋温度差発電に利用したのが熱電方式である。現在では異種金属の替わりに半導体を用いた素子が開発されているが、少温度差を利用する海洋温度差発電では変換効率が低く、まだ実用的ではない。